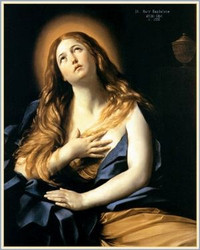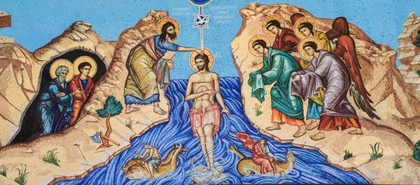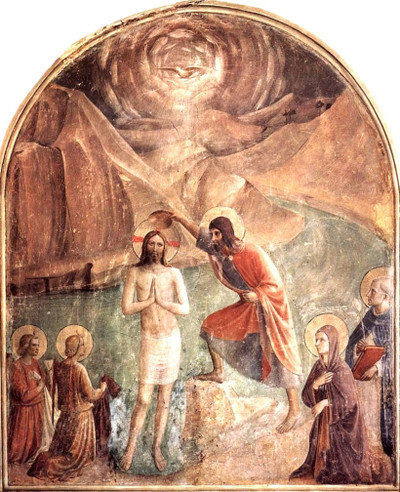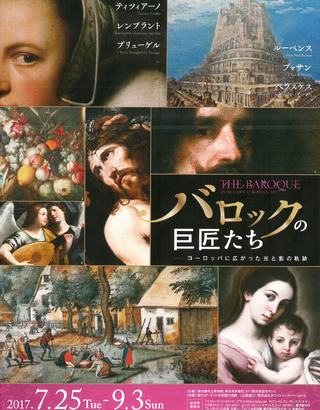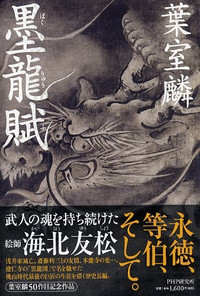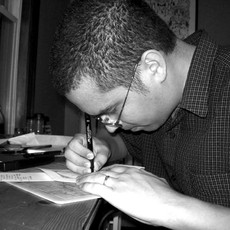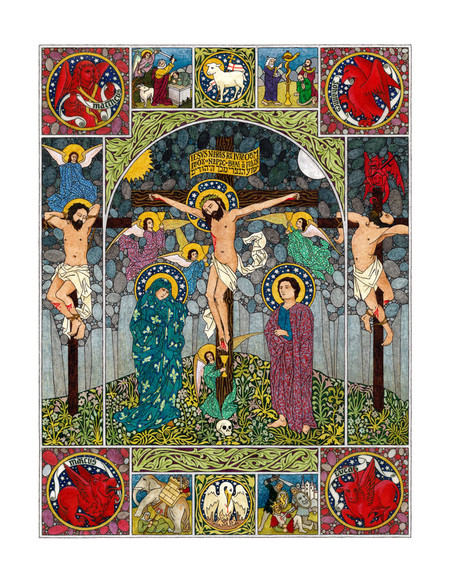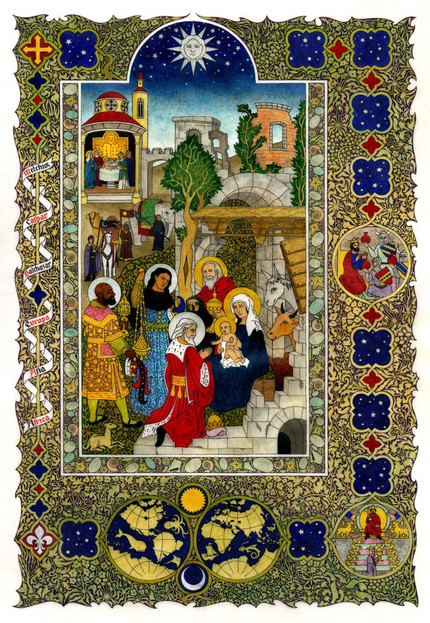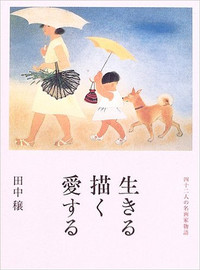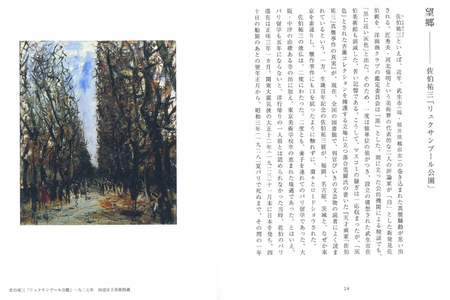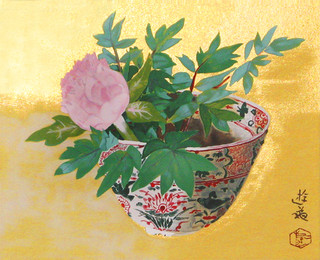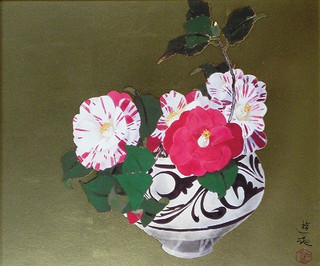歌舞伎

今映画『国宝』が大ヒットしているようですね。今まで歌舞伎に触れることのなかった若者にも刺激を与えているようです。歌舞伎を広めるためにもとても良いことだと思います。團十郎さんもぼたんさんや新之助さんに観るよう薦めたとか。
私は小学生の頃から日本舞踊(藤間流)を習っていたので、歌舞伎が大好きです。学生時代京都に住んでいた時にはよく南座へ歌舞伎を観に行きました。でも京都を離れると同時に歌舞伎鑑賞も遠のいてしまいました。
ちなみに昭和40年代の頃は三之助(六代目市川新之助・四代目尾上菊之助・初代尾上辰之助)にとても人気がありました。私はなぜか六代目市川染五郎(現:二代目白鸚)ファンでしたが。ここ田舎で歌舞伎ファンの中学生は私くらいだったかもしれません。
映画『国宝』も観たいですが、やはり歌舞伎舞踊や歌舞伎の舞台を観たいですね。